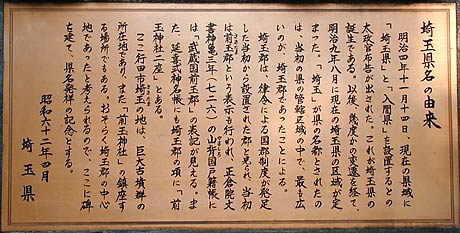明治4年(1871)の廃藩置県で設けられた埼玉県、入間県の
県庁所在地は、それぞれ岩槻、川越であった。入間県は
群馬県(現在の群馬県とは区域が異なる)と合併し、明治6年には
熊谷県に改められている。これは入間県と群馬県の県令(国が任命)が
同一人物だったからという、信じられないほど単純な理由による。
熊谷県は面積が埼玉県の10倍近い広範囲な区域であった。
熊谷県の県庁は、熊谷寺(ゆうこくじ、熊谷市仲町、熊谷次郎直実に
由来のある寺)に置かれた。明治9年(1876)8月、埼玉県と熊谷県が
合併し(この時に群馬県の区域を分離した)、現在の埼玉県の県域が定まった。
しかし、埼玉県の県庁所在地については明治19年(1886)に
熊谷への移転問題が起こるなど、正式に浦和に定められたのは、
じつに明治23年のことである。
ちなみに、明治2年から明治4年までの間は、埼玉県の行政区域は、
非常に交錯していて、じつに6つもの県が存在していた。
忍県(現.行田市)も、そのうちの一つであった。
わずか2年間だが、行田市はかつて県庁所在地だったのだ。