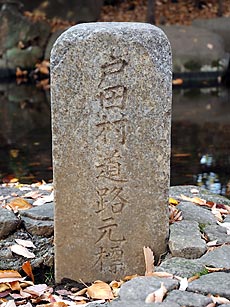吹上町と鴻巣市に設置された道路元標で、見つかっていないのは下表のとうり。
| 区分 |
町村名 |
設置場所 |
現在の住所 |
備考 |
| 吹上町 |
吹上村 |
吹上字中耕地2682 |
不明 |
旧中山道、吹上小学校の付近? |
| 鴻巣市 |
鴻巣町 |
鴻巣字西側2818 |
不明 |
旧中山道、[駅入口]交差点? |
| 〃 |
箕田村 |
箕田字富士山334 |
旧中山道、箕田小学校の付近 |
|
(補足1)太井村(現在の熊谷市、行田市、吹上町)、下忍村(現在の行田市、吹上町)、
笠原村(現在の鴻巣市)は北埼玉郡に属した。
太井村、下忍村、笠原村の道路元標は現存する。→北埼玉郡の道路元標
(補足2)鴻巣市滝馬室の荒川の周辺には、几号の付けられた古い仕様の水準点(内務省、昭和五年)が
2基現存している。それらは昭和初期に完了した荒川の河川改修のさいに、測量の補助水準点として
設置されたと思われる。道路元標と同様に希少な存在である。

↑小谷村道路元標 北足立郡吹上町小谷
小谷小学校(こや)の南西、消防団
第4分団の西側の交差点に残っている。
地上高は49cm、背面に大正十三年。
ここは旧小谷村役場の跡地であり、
付近には旧小谷村史碑が建てられている。
北足立郡小谷村は明治22年(1889)に
小谷村、三町免村、前砂村、明用村が
合併して誕生。小谷村は昭和29年に
吹上町と合併した。 |

↑田間宮村道路元標 埼玉県鴻巣市北中野
田間宮小学校(たまみや)の南側の市道に
残っている。25cm角、地上高47cm。
側面には、大正十四年二月一日とある。
この地点から西側200mには
荒川の左岸堤防が位置する。
北足立郡田間宮村は、明治22年に
糠田村、大間村、宮前村、登戸村、
北中野村が合併して誕生。
昭和29年には鴻巣市と合併した。 |

↑馬室村道路元標 鴻巣市原馬室(まむろ)
馬室小学校前の付近、谷津不動尊前の
T字路(なのはな通)から東へ150mの
地点に残っている。なのはな通から400m
西には荒川の河道があり、そこには
原馬室橋(冠水橋)が架かっている。
元標の脇には消火栓と柳の大木がある。
元標は25cm角、地上高36cm。
馬室村は原馬室村と滝馬室村が
合併して、明治22年に誕生。
昭和29年には鴻巣市と合併。
馬室村青年団が建てた道標が2基残る。 |

↑常光村道路元標 鴻巣市下谷
常光小学校(じょうこう)とJA常光支所の
向かいの道路脇にある。25cm角、
高さは59cm。道路元標の脇には
普門品供養塔(天保十一年建立)も
残っている。この道路(市道)は県道38号と
312号線を結んでいるが、元は旧街道の
ようで、500m北西には寛政九年建立の
道標(像付き、供養塔を兼ねる)もある。
北足立郡常光村は常光村、上谷村、
下谷村、西中曽根村が合併し明治22年に
誕生した。昭和29年には鴻巣市と合併。 |
北本市の道路元標

↑石戸村道路元標 北本市荒井三丁目
県道57号さいたま鴻巣線、JA石戸支所の
前に残っている。22cm角、高さは120cm。
これは旧石戸村道路元標として、北本市の
歴史資料に指定されているが、正確には
道路元標ではなく道標。昭和初期の建立の
ようで、正面に元標とあり、石戸青年団、
農友会などの文字が読み取れる。
石戸村は下石戸上村、下石戸下村、
石戸宿村、高尾村、荒井村が合併して
明治22年に誕生した。昭和18年に中丸村
と合併し、北本宿村となった。 |

↑中丸村道路元標 北本市宮内七丁目
中丸小学校の南側、県道312号下石戸上・
菖蒲線の脇、北本市商工会館の隣にある。
書式が[道路元標 中丸村]と変わっている
うえに、大きさも標準的な元標に比べて、
かなり小さい。希少価値が高い逸品だ(笑)。
幅21cm、奥行き20cm、高さ58cm。
北足立郡中丸村は北中丸村、山中村、
東間村、本宿村、深井村、宮内村、古市場村、
常光別所村、花ノ木村が合併して
明治22年に誕生した。昭和18年には
石戸村と合併し、北本宿村となった。 |
桶川市、上尾市、伊奈町に設置された道路元標で、見つかっていないのは下表のとうり。
| 区分 |
町村名 |
設置場所 |
現在の住所 |
備考 |
| 桶川市 |
加納村 |
坂田字向951 |
県道311号、JA加納の北側 |
桶川高校入口 |
| 上尾市 |
上尾町 |
上尾宿イ仲宿261 |
旧中山道、[上尾駅入口]交差点? |
町役場は氷川鍬神社内 |
| 〃 |
原市町 |
原市字五734 |
県道5号、相頓寺の東側 |
|
| 〃 |
上平村 |
西門前字東579 |
県道87号、JA上平の付近(たぶん旧道) |
道路は拡幅 |
| 〃 |
大石村 |
小泉字天神南747 |
大石小学校の南側付近 |
|
| 〃 |
大谷村 |
大谷本郷字後759 |
県道165号、[大谷本郷]交差点 |
大谷本郷自治会館の西側
または火の見やぐらの付近 |
| 伊奈町 |
小針村 |
羽貫字八幡谷192 |
県道5号、小針神社の西側付近? |
|
| 〃 |
小室村 |
小室字元宿7981 |
県道311号、バス停[元宿]の付近 |
小室小学校から北へ150m |

↑桶川町道路元標 桶川市寿二丁目
旧中山道の桶川駅前交差点内にある。
元標の正面が旧中山道に向いている。
25cm角、地上高は65cm。
旧中山道沿いには、旧旅籠や蔵造りの
商家等もあり往時の面影が残っている。
ここから北西へ300mの東和銀行の
付近には近年に建てた道標があり、
中山道 桶川宿、左 上尾宿三十四町、
右 鴻巣宿一里三十町と記されている。
北足立郡桶川町は明治22年に桶川宿、
大谷領町谷村、上日出谷村、
下日出谷村が合併して誕生した。 |

↑川田谷村道路元標 桶川市川田谷
県道12号川越栗橋線の川田谷歩道橋から
北へ約50mの住宅地の中には、川田谷村
(かわたや)の村役場が残っている(廃屋)。
元標は役場入口の西側の道路脇にある。
旧村役場の建物と道路元標が一緒に
残っている例は、極めて珍しい。
幅26.5cm、奥行25cm角、高さは44cm。
背面には昭和六年四月と記されている。
旧川田谷村は明治22年に北足立郡
川田谷村となった。
昭和30年に桶川町と合併した。 |

↑平方村道路元標 上尾市平方(ひらかた)
県立上尾橘高校から南へ200mに橘神社が
ある。元標は県道57号線(新平方道)の
上尾橘高入口交差点の中、橘神社の鳥居脇に
設置されている。25cm角、高さは36cm。
なお、橘神社の旧名は氷川神社であり、
旧平方村(明治22年以前)の村社であった。
北足立郡平方村は、旧平方村、西貝塚村、
上野村、上野本郷村、平方領領家村が
合併して明治22年に誕生した。
昭和3年には平方町となり、その後、
昭和30年に上尾町と合併した。 |
さいたま市の道路元標、見つかっていないのは下表のとうり。
| 区分 |
町村名 |
設置場所 |
現在の住所 |
備考 |
| 北区 |
大砂土村 |
土呂字稲荷905 |
JA大砂土の付近? |
|
| 日進村 |
上加字宮ノ腰1858-2 |
日進町二丁目、日進神社の付近 |
|
| 大宮区 |
大宮町 |
大宮字大宮3797 |
|
|
| 西区 |
指扇村 |
高木字稲荷前449-2 |
JA指扇の付近? |
|
| 三橋村 |
並木字前1392-3 |
三橋小学校の付近 |
JA三橋は役場跡 |
| 見沼区 |
片柳村 |
御蔵字小山1545-2 |
片柳郵便局の付近 |
|
| 春岡村 |
深作字本村3410 |
春岡公民館の付近 |
道路は拡幅 |
| 桜区 |
大久保村 |
五関字古貝戸140 |
大久保支所の付近 |
|
| 土合村 |
西堀字里1969 |
土合小学校の付近 |
JA敷地内に土合村役場跡の碑 |
| 南区 |
谷田村 |
太田窪字善前北1740 |
産業道路、善前バス停の付近 |
|
| 緑区 |
尾間木村 |
大間木字会ノ谷620-1 |
県道235号線、会の谷バス停の付近 |
|
| 大門村 |
大門字東裏2666 |
国道463号線、大門交差点の付近 |
|

↑宮原村道路元標
さいたま市北区宮原四丁目
JA宮原支店の敷地内。旧中山道に
面した歩道側、記念植樹の脇にある。
元標の正面が旧中山道に向いている。
25cm角、地上高は65cm。JA宮原支店の
敷地内には石造りの古い水準点(水準點、
四八五号、21cm角)も設置されている。
北足立郡宮原村は明治22年に加茂宮村、
吉野原村、奈良瀬戸村、大谷別所村が
合併して誕生した。宮原とは加茂宮村の
宮と吉野原村の原を合わせたものだろう。
昭和15年に大宮町や日進村と合併し
大宮市となった。 |

↑七里村里程標
さいたま市見沼区風渡野(ふっとの)646
東武野田線の七里駅から東へ150mのY字路に
残っている。花崗岩製の39cm×37cmの角柱で、
高さは約270cm。里程標なので道路元標よりも
サイズは大きい。昭和5年12月10日に設置。
七里停車場是ヨリ二丁 左 大門鳩谷みち、
右 原市蓮田みち等と刻まれている。
背面には停車場道寄付者16人の名前があるが、
これは土地を提供した人々だろう。
北足立郡七里村は膝子村、東宮下村、大谷村、
新堤村、猿ヶ谷戸村、風渡野村、東門前村が
合併して、大正2年に誕生した。
昭和30年に大宮市へ合併している。 |

↑七里村の道路元標?
さいたま市見沼区東門前
七里村の道路元標は東門前字道際290に
設置された。現在、近傍には東門前第一自治会館が
あり、その敷地内に道路元標らしき石が
確認できる。水道の前に数個の敷石が
埋められていて、そのうちの一つの形状が
道路元標とよく似ている。頂部には丸みがあり、
大きさも27cm×65cmと道路元標の規格に近い。
ただし、埋設されているので七里村を
示す刻字は確認できない。
また、材質は花崗岩ではないようで、背面には、
こぶ出しに似た仕上げがなされているので、
道路元標だと断言はできない。 |

↑植水村道路元標
さいたま市西区中野林 さいたま市
植水支所の敷地内、民具収蔵庫の前に
ある。25cm角、地上高は68cm。
現在は58cm角、高さ30cmのコンクリート
台座の上に固定されている。
北足立郡植水村は明治22年に植田谷領
本村、水判土村(みずはた)、佐知川村、
中野林村、飯田村、三条町村、島根村が
合併して誕生した。植水とは植田谷領の
植と水判土村の水を合わせたのだろう。
昭和30年に大宮市と合併した。 |

↑馬宮村道路元標
さいたま市西区西遊馬
さいたま市馬宮支所の敷地内にある。
25cm角、地上高は66cm。
下部には49cm角のコンクリート基礎。
北足立郡馬宮村は西遊馬村、土屋村、
二ッ宮村、飯田新田、植田谷領本村新田が
合併して、明治22年に誕生した。
馬宮とは西遊馬の馬と二ツ宮の宮を
合わせた命名。馬宮村は昭和30年に
大宮市と合併した。 |
|

↑浦和町道路元標 さいたま市浦和区
高砂二丁目 JR浦和駅の西口から西へ
250mの地点。旧中山道とさくら草通りが
交差する付近、ユザワヤの脇にある。
この元標は昭和57年に復刻したもの
だが、復刻がいい加減であり、正面には
道路元標とあるのみで、市町村名は
記されていない(注)。北足立郡浦和町は
浦和宿が基になり、明治22年に誕生した。
浦和町は県庁所在地であると同時に
北足立郡の郡役所も置かれていた。
昭和9年には市制を公布し浦和市となった。
川越市、熊谷市、川口市に次いで4番目だ。 |

↑木崎村道路元標
さいたま市浦和区領家四丁目
県道35号川口上尾線(産業道路)の
領家交差点から北へ100m、長覚寺の門前、
民家の角にある。ここから1.5Km南東には
駒場スタジアムが位置する。元標は25cm角、
地上高60cm。コンクリート基礎の上に
置かれている。北足立郡木崎村は
北袋村、上木崎村、下木崎村、瀬ヶ崎村、
木崎領領家村、駒場村、本太村、針ヶ谷村が
合併して明治22年に誕生した。
村名は近世の木崎領に由来すると思われる。
昭和8年に北袋村は大宮町と合併、
残りは浦和町と合併した。 |

↑六辻村道路元標 さいたま市辻三丁目
国道17号線の[六辻]交差点付近、
六辻交番の脇にある。文字どおり、
旧中山道の辻であり、ここから南には
辻の一里塚跡が残る。
元標は25cm×26cm、地上高56cm。
北足立郡六辻村は辻村、白幡村、
根岸村、別所村、文蔵村、沼影村が
合併して明治22年に誕生した。
昭和13年には町制を発布して
六辻町となった。
昭和17年に浦和市と合併した。 |

↑三室村道路元標 さいたま市緑区三室
さいたま市三室支所の敷地内、合併記念碑(昭和15年
建立)の脇に放置されている。
25cm角、全長は90cm。
北足立郡三室村は明治22年に三室村と
道祖土村(さいど)が合併して誕生した。
昭和15年には浦和市へ合併した。 |

↑野田村道路元標 さいたま市緑区代山
八幡宮の敷地内、手水鉢の脇に放置されている。
当初の設置場所は代山字宮ノ台108なので、県道105号線の
野田小交差点付近にあったと思われる。
25cm角、全長は75cm。北足立郡野田村は
上野田村、中野田村、大崎村、南部領辻村、代山村、
寺山村、高畑村、染谷村(一部)が合併して、明治22年に誕生した。
昭和31年には戸塚村、大門村と合併し美園村となっている。 |
(注)オリジナルの元標には、市町村名は記されてなかったということなのだろうか。
ともかく、市町村名がないので、この復刻道路元標が浦和町の頃を
対象にした物なのか、浦和市になってからの物なのか、不明である。
大正9年埼玉県告示第75号(埼玉県報799号)によれば、
浦和町の道路元標は浦和町稲荷丸2266の1番に設置されていた。
現在は稲荷丸という地名は残っていない。
ちなみに埼玉県の県庁所在地は昭和8年まで、浦和町だったが、
市ではなく町が県庁所在地であるのは、全国でも極めて稀な例であった。

↑蕨町道路元標 蕨市中央五丁目9
旧中山道と蕨駅前通りの交差点、
セブンイレブン脇の歩道にある。
25cm角、地上高57cm。
左側面には埼玉縣とあるが、これは
埼玉県の蕨町という意味であり、
元標を設置したのは蕨町である。
元標の脇には説明板と中山道蕨宿の
プレートが併設されている。
北足立郡蕨町は蕨宿と塚越村が
合併して、明治22年に誕生した。
昭和34年には市制を公布し蕨市となった。
全国で最も面積の小さい市は
1889年以降、市域に変更がない。 |
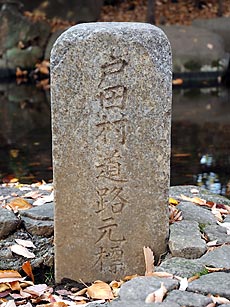
↑戸田村道路元標 戸田市上戸田四丁目
後谷公園の徒渉池の畔に建つ。
明らかに移築されたもの。
25cm角、地上高56cm。
北足立郡戸田村は上戸田村、下戸田村、
新曽村が合併して明治22年に誕生した。
昭和16年に戸田町となり、
昭和32年には美笹村と合併して
新しい戸田町となったが、2年後に
松本新田、曲本、内谷などが分村し、
浦和市へ合併している。 |
|

↑志木町道路元標
志木市本町一丁目〜二丁目
県道36号保谷志木線(本町通り)の
[本町一丁目]交差点内にある。
25cm角、地上高68cm。背面に埼玉縣と
あるが、これも埼玉県の志木町という意味で
あり、元標を設置したのは志木町である。
新座郡志木町は志木宿がそのまま町制と
なり、明治22年に誕生した。新座郡は
明治29年に北足立郡へ編入となった。
昭和19年には北足立郡志木町、内間木村と
入間郡宗岡村、水谷村が合併して北足立郡
志紀町(しき)が誕生した。志紀町は
昭和23年に分村したため、再び北足立郡
志木町に戻ったが、昭和30年には
宗岡村と合併して足立町となった。 |

↑白子村道路元標 和光市白子二丁目19
白子郵便局から北東へ150m、滝坂の
交差点にある。
25cm角、地上高66cm。背面に埼玉縣。
新座郡白子村は白子村と下新倉村が合併して、
明治22年に誕生した。新座郡は明治29年に
北足立郡へ編入となった。
白子村は昭和19年には北足立郡新倉村と
合併して北足立郡大和町(やまとまち)と
なった。大和町は昭和45年に市制を施行し、
和光市となったが、紛らわしいことに、
同時期には東京都北多摩郡大和町
(東大和市の前身)が存在した。 |
|
戻る:[道路元標の一覧] [北埼玉郡][南埼玉郡][北葛飾郡][大里郡][深谷市][熊谷市][比企郡][入間郡][児玉郡][秩父郡]