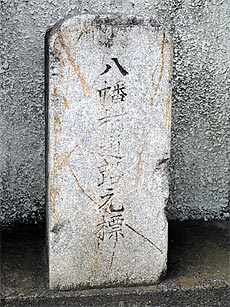さいたま市岩槻区に設置された道路元標で、見つかっていないのは下表のとうり。
| 町村名 |
設置場所 |
現在の住所 |
備考 |
| 岩槻町 |
岩槻2425 |
県道2号(旧国道16号)と国道122号の交差点? |
市役所に村役場跡碑 |
| 河合村 |
平林寺字西422 |
河合小学校と幼稚園の間 |
JA河合脇に村役場跡碑 |
| 柏崎村 |
柏崎字中組865 |
柏崎小学校の北のT字路 |
小学校に村役場跡碑 |
| 和土村 |
黒谷字八幡裏1564 |
和土小学校南側の表忠碑の付近 |
JAに村役場跡碑 |
| 新和村 |
尾ヶ崎字半縄1270 |
新和小学校の北側付近 |
小学校に村役場跡碑 |
 |
←慈恩寺村道路元標
さいたま市岩槻区慈恩寺(じおんじ)
JA慈恩寺支店の北側の三叉路、
地蔵堂の脇にある。村の名前に冠された、
慈恩寺(坂東三十三箇所札所の一つで、
元荒川沿線の観音信仰の中心地)から
北西へ250mの地点だ。元標は
幅25cm、奥行き24cm、地上高80cm。
文字は読めるのだが、頂部の破損が酷い。
元標の脇には宝暦六年(1756)建立の
庚申塔があるが、それは側面が粕壁と
幸手(日光街道の宿場)への道標を
兼ねている。なお、この付近に現存する
江戸時代に建立された道標には
行き先として、慈恩寺が記されたものが
非常に多い。
南埼玉郡慈恩寺村は慈恩寺村、
裏慈恩寺村、表慈恩寺村、古ヶ場村、
徳力村、鹿室村、上野村、南辻村、
小溝村、相原野村が合併して、
明治22年に誕生した。
昭和29年には岩槻町と合併。 |

↑川通村道路元標 岩槻区本町二丁目2-34
現在は岩槻郷土資料館に収蔵されている。
本来は大口地区のJA川通支所(旧村役場の跡地)の
道路脇に設置されていたのだが、道路整備に伴い、
不要となり、郷土資料館に持ち込まれたのだという。
南埼玉郡川通村は南平野村、長宮村、大野島村、
増長村、大口村、大谷村、大戸村、新方須賀村、
大森村が合併して、明治22年に誕生した。
昭和29年には岩槻町と合併。 |
菖蒲町に設置された道路元標で、見つかっていないのは下表のとうり。
| 町村名 |
設置場所 |
現在の住所 |
備考 |
| 菖蒲町 |
菖蒲171 |
県道313号、仲横(ちゅうおう)交差点付近 |
道路は拡幅 |
| 三箇村 |
三箇字中1252 |
国道122号、[釜屋前]バス停付近 |
三箇小学校の敷地内には村立図書館 |

↑小林村道路元標 南埼玉郡菖蒲町小林
小林は[おばやし]と読む。
小林小学校前交差点(県道310号線と
県道312号線が交差)から北西へ50m、
町道のT字路にある。
25cm角、地上高64cm。
標石の隅が面取りされているのが特徴。
南埼玉郡小林村は明治22年(1889)に
誕生。昭和29年には菖蒲町と合併した。
つまり江戸時代以降、菖蒲町と合併する
まで村域は変わらなかった。
村内のほぼ中央に野通川が流れる。 |

↑栢間村道路元標 菖蒲町下栢間(かやま)
県道77号行田蓮田線の脇、栢間小学校の
校門前に設けられている。幅26cm、
奥行き29cm(現存最大)、地上高は
59cm。これも四隅が面取りされている。
栢間小学校は江戸時代に、この地域を
治めていた内藤氏の陣屋の
跡地だという。南埼玉郡栢間村は
上栢間村、下栢間村、柴山枝郷が
合併して明治22年(1889)に誕生した。
昭和29年には菖蒲町と合併した。 |
白岡町に設置された道路元標で、見つかっていないのは下表のとうり。
| 町村名 |
設置場所 |
現在の住所 |
備考 |
| 日勝村 |
上野田大日139 |
大日橋(隼人堀川)の付近 |
橋詰にJA日勝 |

↑大山村道路元標 白岡町荒井新田
大山小学校の正門の西側にある。
幅25cm、奥行き26cm、地上高は10cm。
すぐ脇(写真の奥)には隼人堀川が
流れている。大山小学校の敷地内の
大山民俗資料館は旧尋常高等小学校の
木造校舎を動態保存したもの。
南埼玉郡大山村は上大崎村、下大崎村、
柴山村、荒井新田村が合併して、
明治22年に誕生した。昭和29年には
白岡町と合併したが、上大崎村は
分村し、菖蒲町と合併した。 |

↑篠津村道路元標 白岡町篠津(しのづ)
篠津小学校の正門から西へ100mの三叉路に
ある。大正13年8月建立。付近の表忠碑
(昭和6年、帝国在郷軍人会)によると、ここは
幸手町道、菖蒲町道、原市町・岩槻町道の
交差点である。すぐ脇には隼人堀川が流れている。
元標は28cm角、地上高64cm。
石ではなくコンクリート製、書体も独特である。
南埼玉郡篠津村は篠津村、野牛村、
白岡村、寺塚村、高岩村が合併して、
明治22年に誕生した。昭和29年には
白岡町と合併。 |
久喜市、蓮田市に設置された道路元標で、見つかっていないのは下表のとうり。
| 区分 |
町村名 |
設置場所 |
現在の住所 |
備考 |
| 久喜市 |
久喜町 |
久喜新383 |
久喜市中央三丁目、停車場道の交差点 |
2000年頃に紛失 |
| 〃 |
太田村 |
吉羽字沼向1357 |
市立図書館の南東付近 |
|
| 〃 |
江面村 |
北青柳字新道下1336 |
東北自動車道、久喜I.Cの南側 |
|
| 蓮田市 |
綾瀬村 |
閏戸字野久保265 |
国道122号、[蓮田浄水場]交差点の付近 |
埋蔵文化財室が役場跡地 |
| 〃 |
黒濱村 |
黒濱字中野原3068 |
黒浜小学校の西側 |
JAが役場の跡地 |

↑清久村道路元標 久喜市上清久(きよく)
久喜市西公民館の敷地内、北側の
フェンス際にある。公民館の所在地は
上清久の飛地(周囲は六万部と所久喜)。
元標は25cm角、地上高60cm。
これも四隅が面取りされている。
コンクリートの台座の上に置かれているのは、
移築されたからだろう。おそらく当初は
ここから100m南側の県道12号川越
栗橋線の付近に設置されていたと
思われる。南埼玉郡清久村は上清久村、
下清久村、六万部村、所久喜村、
北中曽根村が合併して、明治22年に誕生。
昭和29年には久喜町と合併。 |

↑平野村道路元標 蓮田市井沼
県道77号行田蓮田線の路傍、平野小学校の
西側のT字路にある。25cm角、地上高60cm。
この元標も四隅が面取りされている。
ここから北側400mには元荒川、南側300mには
見沼代用水が流れているが、県道の路線は
低地ではなく微高地(台地の部分)を通っている。
なお、この付近には江戸時代に建立された、
石橋供養塔が数多く残っている。
南埼玉郡平野村は上平野村、高虫村、
駒崎村、井沼村、根金村が合併して、
明治22年に誕生した。
昭和29年には蓮田町と合併。 |
宮代町と春日部市(南埼玉郡)に設置された道路元標で、見つかっていないのは下表のとうり。
| 区分 |
町村名 |
設置場所 |
現在の住所 |
備考 |
| 宮代町 |
百間村 |
百間西原組字西原460 |
西原団地の東側、山崎地区との境界付近 |
|
| 〃 |
須賀村 |
和戸字宿251-3 |
和戸公民館が村役場の跡地 |
|
| 春日部市 |
粕壁町 |
粕壁6110 |
この地番は残っていない |
春日部中学校の付近か? |
| 〃 |
豊春村 |
道順川戸字隅田川縁37 |
豊春小学校の付近、県道2号線 |
付近に火の見櫓 |
| 〃 |
内牧村 |
内牧字高野4399-1 |
内牧公民館の付近、県道78号線 |
付近に火の見櫓 |
| 〃 |
武里村 |
備後字須賀929 |
武里小学校の北、須賀公民館の付近 |
|
越谷市に設置された道路元標で、見つかっていないのは下表のとうり。
| 町村名 |
設置場所 |
現在の住所 |
備考 |
| 越ヶ谷町 |
越ヶ谷4672 |
この住所は存在しない。越谷駅前通の付近か? |
道路は拡幅 |
| 大澤町 |
字辻721 |
大沢小学校の付近か? |
|
| 出羽村 |
四丁野字四丁野1881 |
出羽小学校の付近、四丁野通 |
|
| 大袋村 |
大竹字東畑158 |
大袋公民館の付近 |
|
| 櫻井村 |
大泊字堰場730 |
桜井小学校と桜井公民館の間 |
|
| 荻島村 |
南萩島字戸井775 |
萩島小学校の北方、県道48号線 |
|
| 蒲生村 |
蒲生字中道3197 |
|
|

↑新方村道路元標 越谷市大杉
県道102号平方東京線の新方小学校
交差点内にある。
26.5cm角、地上高は36cm。
南埼玉郡新方村(にいがた)は北川崎村、
大吉村、船渡村、大松村、大杉村、
弥十郎村、向畑村が合併して、
明治22年に誕生した。村名は中世の
古い荘名に由来する。近世以降の
水防・水利共同体としての新方領は
増林村も含む、もっと広い区域である。
新方村は昭和29年に越谷町と合併した。 |

↑増林村道路元標 越谷市増林3685付近
増林駐在所(ますばやし)から北西へ
200m、県道102号線の道路脇にある。
ここは旧村役場の跡地だという。
26cm角、地上高は65cm。
南埼玉郡増林村は増林村、増森村、
中島村、東小林村、花田村が合併して、
明治22年に誕生した。昭和29年には
越谷町と合併。なお、増林村は古利根川と
元荒川が中川へ合流する地域なので、
粘土や砂が多く堆積していたため、
明治時代後半に数多くの煉瓦工場が
創設された。
|

↑大相模村道路元標 越谷市大成町一丁目
県道52号越谷流山線の[大相模小学校入口]
バス停の対面にある。25cm角、地上高52cm。
元標面が道路に背を向けているので、
移築されたのだと思われる。大相模村の
村役場はここから200m北の観音寺にあった。
観音寺の北側から元荒川の右岸までは
約300mあるが、この区域は近年まで遊水池だった。
南埼玉郡大相模村は東方村、西方村、
見田方村、南百村、四条村、別府村、
千疋村が合併して明治22年に誕生した。
村名は中世の大相模郷に由来する。
昭和29年には越谷町と合併した。 |
 |
←川柳村道路元標 越谷市川柳町五丁目282付近
県道380号線の麦塚交差点の脇、
女体神社の入口にある。
この元標は復刻されたもの。
元標は25cm角、地上高57cm。
写真の右隅に見えるのは破損した旧元標の跡。
花崗岩製で26cm角であったことがわかる。
南埼玉郡川柳村は柿ノ木村、南青柳村、
麦塚村、伊原村が合併して、明治22年に誕生した。
昭和29年8月には北足立郡草加町と合併したが、
同年11月に麦塚村、伊原村は分村して、
越谷町と合併した。 |
八潮市に設置された道路元標で、見つかっていないのは下表のとうり。
| 町村名 |
設置場所 |
現在の住所 |
備考 |
| 潮止村 |
伊勢野字根通779 |
この地番は残っていない、潮止小学校の付近か? |
|

↑八條村道路元標 八潮市八條
八條小学校から東へ200m、県道102号
平方東京線の脇にある。道路元標が
置かれた市道は、中川の旧堤防である。
25cm角、地上高は54cm。
南埼玉郡八條村(はちじょう)は八条村、
鶴ヶ曽根村、松之木村、伊草村、小作田村、
立野掘村の6村が合併して、明治22年に
誕生した。昭和31年には立野掘村を除く
旧5村が八幡村、潮止村と合併し、
南埼玉郡八潮村となった。
なお、立野掘村は草加市へ合併した。 |
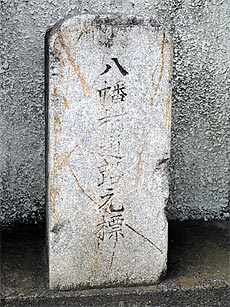
↑八幡村道路元標 八潮市中央三丁目
県道54号線(旧道)の道路脇、
八幡図書館の塀の中にある。
ここは旧八幡村役場の跡地だという。
25cm角、地上高は63cm。
南埼玉郡八幡村(やわた)は上馬場村、
中馬場村、大原村、大曽根村、浮塚村、
西袋村、柳之宮村、南後谷村の8村が
合併して、明治22年に誕生した。
昭和31年には八条村、潮止村と合併し、
南埼玉郡八潮村となった。 |
|
戻る:[道路元標の一覧] [北埼玉郡][北葛飾郡][北足立郡][大里郡][深谷市][熊谷市][比企郡][入間郡][児玉郡][秩父郡]